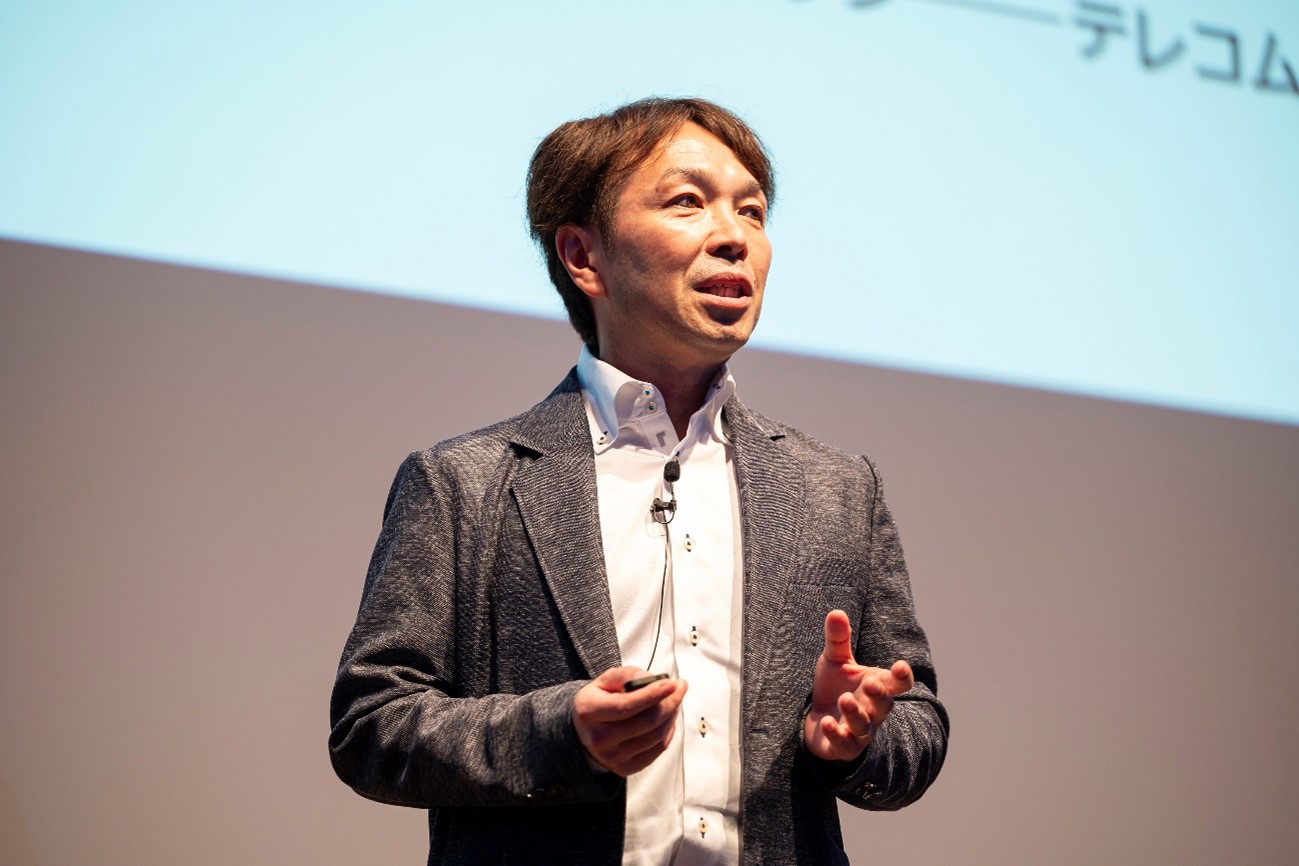さて、今回は6月17日にリリースされ、7月23日、29日、8月5日にお客様、そしてパートナー様向けにローンチイベントを開催させていただいたイベントレポート第2回目です。今回はVCF 9の具体的な機能アップデートをご紹介いたします。
■VCF 9の技術的なトピック徹底解説
続いては、クラウドインフラストラクチャ技術部 部⻑ 大平伸一が登場し、「真のプライベートクラウドを具現化するVMware Cloud Foundation 9」と題して講演を実施。VCF 9の技術的なトピックとして「コアプラットフォームにおけるイノベーション」「モダン・インフラストラクチャ」「クラウドエクスペリエンス」「安全性とレジリエンス」という4つの視点とともに、VCF 9の能力を向上させるPrivate AI Foundation」について詳しく触れました。新機能が盛りだくさんとなっており、VCF 9への期待値を否が応でも高めました。
- コアプラットフォームにおけるイノベーション
VCF 9は、オンプレミス、パブリッククラウド、ソブリンクラウド、エッジコンピューティング、通信キャリアといったあらゆる環境に適用でき、仮想マシン、コンテナ、そしてAI/MLアプリケーションも共存可能です。そして、メモリとサーバのTCO低減率を38%、ストレージのTCO低減率を34%、スイッチングパフォーマンス性能を3倍に向上、パフォーマンスのオーバヘッドが1%未満、vMotionの最適化によってダウンタイムを最小化することに成功していると驚くべき数値を紹介。
この数値を可能にする新技術として、メモリ階層化技術のAdvanced NVMe Memory TieringやCPUコアあたりのパケット処理能力を高めたEnhanced Data Path、クラスタワイドな重複排除技術であるvSAN ESA with Global Deduplicationなどを紹介しました。
- モダン・インフラストラクチャ
VCF 9では、単一のインターフェース運用によって高効率なプライベートクラウドの運用が可能になります。vCenter、NSX Manager、SDDC Manager、VCF Operations、VCF Automationといった全コンポーネント含め、新しいVCF Installerが全てのセットアップをウィザード形式で完了させることができます。「プラットフォーム全体のライフサイクル管理を一本化し、VCFに含まれる全てのコンポーネントが共通のバージョンでリリースされるユニファイドリリースを実現しています」と説明。バージョン違いで複雑な運用を迫られていた管理者にとってはまさに朗報です。
さらに、VCFプラットフォーム全体のヘルスチェックを常時プロアクティブに実施できるよう、Skyline DiagnosticがVCF Operationsに再統合しました。
- クラウドエクスペリエンス
クラウドエクスペリエンスの観点では、従来のAria AutomationとvCloud Directorの統合によってVCF Automationがモダンクラウドポータルとして提供され、ユーザ視点や管理者視点、テナント視点というそれぞれ異なるポータルを用意するなど本格的なクラウドエクスペリエンスを実現します。また、利用者及び開発者向けの新しいセルフサービスポータルとして、アプリケーションカタログとIaaSそれぞれのセルフポータルが備わっています。
他にも、パブリッククラウドのようなIaaSクラウドサービスを即座に提供でき、VMサービスやvSphere Kubernetes Service、VMイメージ、ネットワークサービスといったコアサービスとともに、各種拡張サービスを用意。Kubernetes Serviceとしては、ストレージ(CSI)、ネットワーク(Antrea/Calico)、vSphere CPIなどが含まれるコアパッケージと、External DNSやCert Manager、Harborなどの標準パッケージが提供されます。
実際に、Webポータルから仮想マシンを作成し、OSイメージ選択、CPU/メモリサイズ指定、ネットワーク設定を行うデモ動画を交えながら、容易なセルフサービスであることを紹介しました。
- 安全性とレジリエンスの確保
安全性という観点では、NISTの特定、防御、検知、対応、復旧というサイバーセキュリティフレームワークに適用しており、エンドツーエンドのセキュリティ機能を提供すると紹介しました。
「Security Operationダッシュボードを新たに新設し、プラットフォームへのログイン成功・失敗数や権限変更をリアルタイムで監視し、異常を検知します。CISやNIST SP 800-171などの業界ベンチマークに対応し、ガイドラインに逸脱していないかをダイナミックに検査することも可能です。構成管理機能とともに、業界に先駆けて行ってきたマイクロセグメンテーションをさらに進化させ、トラフィックとルールの比較によってグレーゾーン通信を検知、推奨ファイアウォールルールの自動生成の提案から自動反映もサポートします」と語ります。
また、ハイパーバイザー組み込み型のIDS/IPSやNDRが備わっており、AIチャットボット機能を使って対話しながらの迅速なインシデント対策が可能です。一度だけの書き込みが許可されたvSAN ESAのスナップショットによってランサムウェア対策としても有効に機能することを力説しました。
- VCF 9の能力を向上させるPrivate AI Foundation
VCF 9では、ニーズが高まる生成AIアプリケーションに対応するため、NVIDIAと共同開発したソリューションを提供します。セルフサービス自動化やGPUの利用状況の可視化と監視、検索拡張生成であるRAGサービスの容易な作成、そして学習能力を高めるベクトル型DBをパッケージに含めるなど、Private AIを整備するためのインフラづくりを支援する環境が整っていると説明しました。まさにこれからの時代に求められる生成AIへの展開に、参加者も興味津々の様子でした。
イベントレポートシリーズの最終回では、VCF 9の活用とクラウドモダナイゼーションの実践的なアプローチについてご紹介いたします。